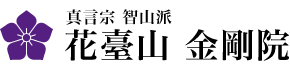近年では、墓じまいをした後に遺骨を【合祀墓(ごうしぼ)】へ納めるケースが増えています。
合祀墓へ納骨すれば、その後はずっと寺院で遺骨を供養してくれるので安心です。
しかし、合祀墓にはメリットだけでなく大きなデメリットもあるので注意が必要です。
本記事では【合祀墓のメリットとデメリット】について紹介しています。
お墓の後継者がいないので墓じまいをしたい、お墓を持ちたくない、という方は最後まで読んでみてください。
《合祀墓とは何?》
合祀墓の説明をする前に、まずは『合祀(ごうし)』について説明します。
『合祀』とは、亡くなった人の遺骨を、血縁関係のない他人の遺骨と一緒に埋葬することをいいます。
合祀をすればお墓を持つ必要がないため、お墓に関するさまざまな問題が解消されます。
また、多くの場合、合祀には《永代供養》がセットになっていますので無縁仏になってしまう心配もありません。
このようなことから、お墓を持つ予定がない人や墓じまいをする人は合祀墓を選んでいます。
ちなみに、合祀と似たような言葉に『合葬(がっそう)』がありますが、下記のとおり両者は少しだけ意味が異なります。
- 『合祀』:骨壺から遺骨を出して他の人の遺骨と一緒に埋葬する
- 『合葬』:骨壺のままで他の人の骨壺と一緒に納骨する
しかし、合祀と合葬を同じ意味で使用している寺院や霊園も多いので、合祀墓を利用するときには、どのような形式であるかを確認しておきましょう。
《合祀墓のメリット》
合祀墓にはさまざまなメリットがありますので、いくつか紹介します。
【遺骨の供養をすべて寺院に任せられる】
合祀墓には『遺骨の供養をすべて寺院に任せられる』という大きなメリットがあります。
寺院がずっと遺骨の供養をしてくれるので、墓じまいをすれば『お墓の継承者問題』が解消されます。
また、合祀墓を利用するのは、お墓を持つ予定がない人や墓じまいをする人だけではありません。
長期間お墓を使用していると、いずれお墓の中が骨壺で一杯になりますので、一部の遺骨だけを合祀墓へ移す人もいます。
合祀墓へ納骨すれば、寺院が存続する限り故人が無縁仏になることはないので、家族にとっては安心です。
【お墓を管理する手間がない】
合祀墓に納骨をし、墓じまいをすれば《お墓を管理する手間》がなくなります。
お墓を持っていると、墓石の清掃だけでなく、墓地内の清掃や雑草処理も必要です。
墓石は非常に頑丈なものではありますが、それでも定期的に清掃をしないと劣化が早くなってしまいます。
そして、墓地内にも落ち葉や雑草などがあり、それらの清掃をしなくてはいけません。
特に雑草は、3月~10月くらいの期間は生えてきますので除草作業だけでも大変です。
しかし、合祀墓へ納骨し、お墓を手放すことで、お墓の管理をする手間から解放されます。
【金銭的な負担が少ない】
合祀墓は、一般的なお墓に比べると『金銭的な負担』が少なくてすみます。
一般的なお墓を建てるときには、
- 永代使用料(墓地の使用料)
- 墓石の代金
- 墓石設置の工事代金
- その他、寺院や霊園での初期費用
などの費用が必要です。
これらの費用は、墓地の大きさや使用する石の種類、そして石の数にもよりますが、総額で数百万円かかります。
一方で、合祀墓なら、永代供養料や納骨供養料などを合わせても数十万円程度でしょう。
また、合祀墓へ納骨をした後には一切費用がかからない寺院が多いので、金銭的な負担は大幅に軽減されます。
【宗教や宗派を問わない】
合祀墓の多くは、宗教や宗派を問わずに広く受け入れています。
せっかく自宅の近くに合祀墓があっても、それを管理している寺院の宗派に制限されてしまうと利用できないこともあります。
しかし、近年では利用者の要望に応え、宗教や宗派が違っていても合祀墓に納骨してくれる寺院が多いです。
宗教や宗派にこだわらない人、または異なる宗教を信仰する家族にとっては、最寄りの寺院で永代供養ができるので『宗教宗派が不問』の合祀墓はとても便利です。
【いくつかのタイプの合祀墓がある】
お墓の形はどんどん多様化しており、合祀墓にもいくつかのタイプがあります。
昔ながらの形(和型)の合祀墓もあれば、洋風で近代的な形の合祀墓も増えています。
そのため、ある程度は生前の故人の意向に合わせて合祀墓のタイプを選ぶことができます。
【生前の申し込みも可能】
寺院や霊園によっては『合祀墓の生前の申し込み』ができるところもあります。
生前に申し込みをして費用を先に支払っておけば、いざというときに家族の負担を減らせます。
また、近年では『終活』を始める人が増えているので、その一環で合祀墓の生前申し込みをする人が増えています。
《合祀墓のデメリット》
合祀墓は非常に便利なお墓ですが、それなりにデメリットもあります。
メリットだけでなくデメリットもよく理解した上で、合祀墓の利用を検討しましょう。
【見ず知らずの他人の遺骨と一緒に埋葬される】
合祀墓の大きなデメリットは、家族の遺骨が《見ず知らずの他人の遺骨》と一緒に埋葬されることです。
墓じまいをする場合、それまでは《同じ家の先祖や亡き家族》と一緒だったのが、合祀後はまったくの他人の遺骨と一緒になります。
家族の遺骨が他人の遺骨と一緒になることを嫌がる人も多いので、合祀墓の利用は家族でよく話し合って慎重に決めることが重要です。
【合祀した遺骨は取り出せない】
合祀墓で最も注意すべきは、合祀した遺骨は取り出せないということです。
合祀をするときには、骨壺から遺骨を出して埋葬することがほとんどです。
そのため、他人の遺骨と混ざってしまい、後になって特定の人の遺骨だけを取り出すことはできません。
他のお墓へ納骨する、または海洋散骨をするなど、他のかたちで遺骨を供養する可能性があるかどうか、事前によく考えておきましょう。
【親戚への説明が必要】
合祀墓を利用するにあたり、場合によっては親戚への説明が必要となるでしょう。
遺骨は『自家のお墓』へ納骨するのが一般的で、合祀墓へ納骨するのは《やむを得ない事情があるから》というケースが多いです。
そのため、合祀墓へ納骨する場合、親戚から「なぜ合祀にするの?」と聞かれるかもしれません。
そのときに【合祀をする理由】を説明できるようにしておく必要があります。
【花立てや香炉が共用】
合祀墓は、花立てや香炉が共用になっています。
そのため、お盆やお彼岸などの時期は、お墓参りをする人が集中し、
- 花立てがお花でいっぱいになっている
- 香炉の中に、他の人が供えたばかりの線香が残っている
ということもよくあります。
しかし、花立てや香炉が共用であることが、合祀墓の費用が安い理由の1つなのです。
そのため、合祀墓を利用するにあたり、共用部分には多少の不自由があることを辛抱する必要があります。
【管理者の都合で墓所の移動や供養方法の変更がある】
合祀墓は、管理者の都合で墓所の移動や供養方法が変更されることがあります。
合祀墓には、必ず寺院や霊園などの管理者がおり、合祀墓の使用方法や管理方法は管理者が決めます。
そのため、管理者の都合によっては、途中で墓所の場所が変わったり、供養方法が変わることもあるのです。
《まとめ》
合祀は、お墓の後継者問題を解決できたり費用が大幅に抑えられるなどの大きなメリットがあります。
一方で、見ず知らずの他人の遺骨と一緒に埋葬される、遺骨の取り出しができない等のデメリットもあります。
合祀墓の利用を検討するときにはメリットとデメリット、そして故人の意向や家族の希望などを十分に考慮しながら決めましょう。
《金剛院の個別永代供養墓》
金剛院には、他人の遺骨と一緒にならずに永代供養ができる【個別永代供養墓】がございます。
お申し込み時に『墓所使用開始から永代供養までの全ての費用』を先に納めていただくことで《その家専用の永代供養墓》としてご利用いただけます。
また、ご利用開始後は、お墓の維持管理費が一切かかりませんので、ご家族や後代の方々に金銭的な負担をかけずにすみます。
ただし、区画数には限りがありますので「後継者がいなくてお墓を維持できない、でも合祀は何となく気が引ける。」という方はお早めにお問い合わせください。
〖真言宗 智山派 金剛院〗
〒331-0823
埼玉県さいたま市北区日進町1-758
《お問い合わせ・墓所見学のお申込み》
受付時間
9:00 ~ 16:00 【年中無休】
TEL 048-663-6005
★他にもいろんな記事がありますので読んでみてください。