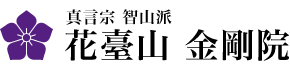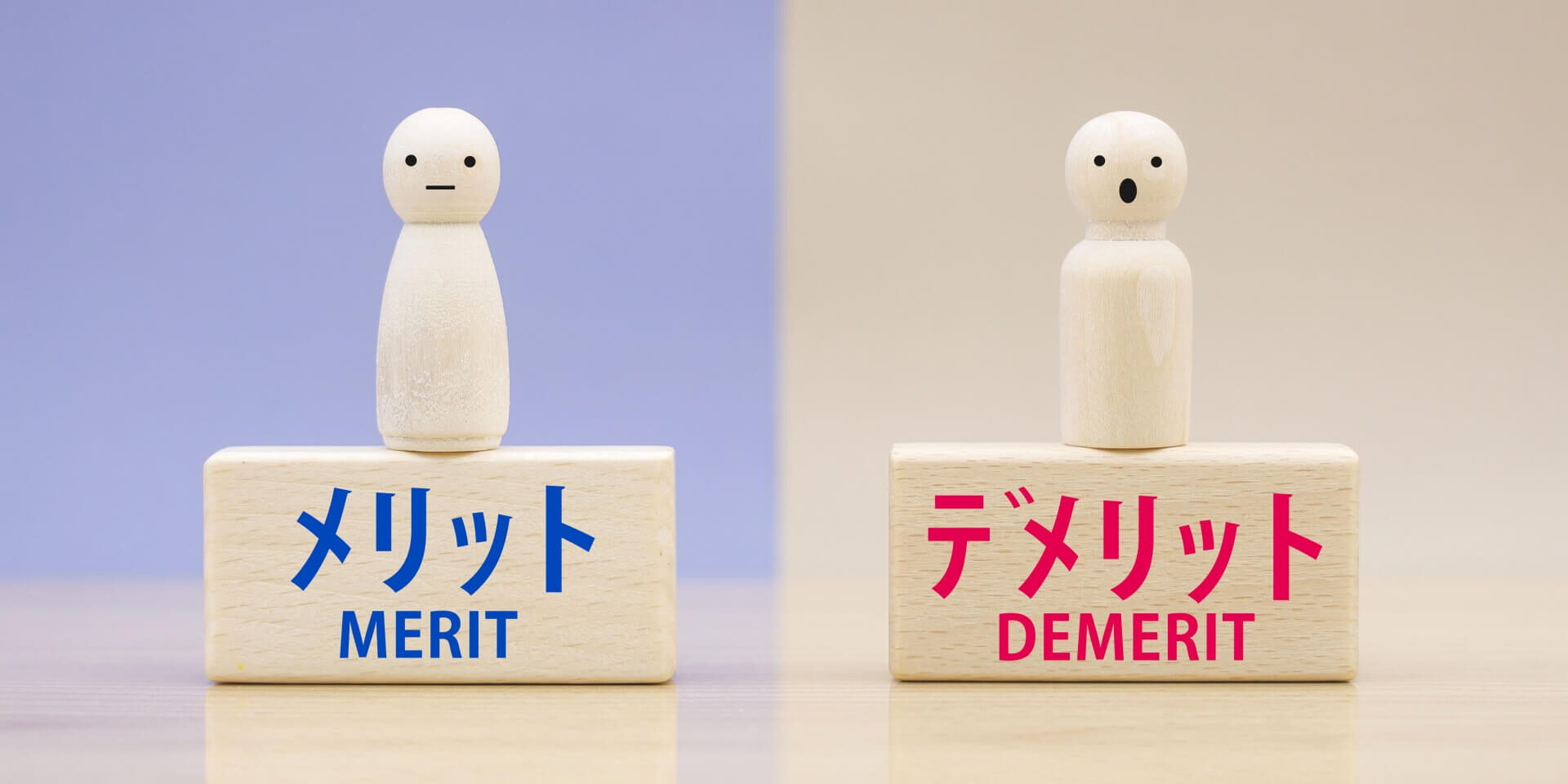初めて家族が亡くなると、新たに『お墓』を建立して遺骨を埋葬するのが一般的です。
しかし、近年ではお墓を持つことを躊躇する人が増えています。
なぜなら、故人が安心して眠れる場所を作ることには深い意義がある反面、お墓の維持管理の手間や費用に対する不安があるからです。
本記事では、お墓を建てることのメリットとデメリットを紹介しています。
大切な人の遺骨をどこへ納めるべきなのか、本記事をご参考にご家族で話し合ってみてください。
《お墓を建てることのメリット》
まずは、お墓を建てることで得られるさまざまなメリットから紹介します。
【故人との繋がりを感じ、心のよりどころになる】
お墓を建てると、故人との繋がりが感じられ、心のよりどころになります。
お墓はこの世とあの世を繋ぐものであり、お墓を通じて私たちの思いが故人に届き、また、故人からのメッセージもお墓を通じて私たちに届けられます。
つまり、お墓を建ててお参りをすることで、故人と向き合い、そして繋がりを感じることができるのです。
そして、故人との繋がりを感じることができれば、そこは家族にとって大事な【心のよりどころ】にもなります。
《関連記事》:お墓は何のためにあるの?お墓の意味と役割
【納骨場所があるので安心】
お墓を建てれば『ちゃんと納骨場所がある』という安心感が生まれます。
お墓を持っていないと、いざというときに納骨場所がなく慌ててしまいがちです。
納骨場所が定まらなければ、供養する場所も定まりません。
もちろん供養はどこでもできますが、供養する場所がちゃんと決まっていることが安心に繋がります。
また、納骨場所が決まっていれば、家族全員にとって『いずれ自分が入る場所』も確保されるので、それも大きな安心材料です。
さらに、お墓があれば親戚にとっても《お参りできる場所》が明確なので分かりやすいです。
【納骨の手続きが早い】
お墓を建てておけば、いざというときに納骨の手続きが早くなります。
地域によりますが、お墓へ納骨するタイミングとしては【49日忌】が多いです。
そのため、お墓を持っていなければ、お葬式が終わった数日後に、まずは墓地の見学などに動き出す必要があります。
それから、寺院や霊園との墓地を取得するための手続き、そして石材店との墓石を建てるための手続きを経て、ようやく納骨の手続きができます。
しかし、納骨場所が決まっていれば納骨の手続きだけですむので、残された家族の負担は少ないです。
【家系の記録を残すことができる】
お墓を建てると、家系の記録を残すことができます。
墓石には、
- 故人の名前
- 死亡時の年齢
- 死亡年月日
- 戒名(法名)
など、その墓地に埋葬された人の情報が彫刻されています。
これにより、簡単なものではありますが、その家の『系譜』が分かります。
【寺院や霊園との繋がりができる】
お墓を建てると、寺院や霊園との繋がりができます。
お墓は寺院や霊園に建てることが多く、墓地使用以後はそれぞれの寺院や霊園との付き合いが始まります。
寺院や霊園との付き合いがあれば、いつでも墓地の仕様や供養に関する相談ができるので安心です。
また、定期的に供養の案内なども来るため、法事を忘れてしまう心配もありません。
【終活の一環になる】
お墓を建てておくことは『終活』の一環になります。
生前にできるだけ家族の負担を減らしておくことは、終活の大事な目的の1つです。
お墓を建てるには大きな費用が必要なので、それを先に済ませておけば家族の負担を軽減できます。
また、自分が入るお墓を事前に用意しておくことで、少し気持ちが楽になり、安心して日々の生活を送ることができます。
《お墓を建てることのデメリット》
お墓を建てることにはデメリットもあります。
意外なデメリットもあるので注意しましょう。
【お墓建立にたくさんの費用がかかる】
お墓を建てると、たくさんの費用がかかるのがデメリットです。
例えば、一般的なお墓の場合、
- 永代使用料(墓地の使用料)
- 墓石の代金
- 墓石設置の工事代金
- その他、寺院や霊園での初期費用
などの費用が必要で、総額で数百万円となるため、まずは『お墓を建てる準備』から始めなくてはいけません。
【維持費が必要】
お墓を持つということは、それを維持するための費用が必要です。
毎年の《管理料》や《恒例行事の費用》などの他にも、
- 生花
- 線香
- 供物
- 交通費
など、お墓参りに関する費用も必要となります。
これらは、お墓参りのたびに発生するもので、塵も積もれば山となります。
※関連記事:寺院や霊園の管理料は『個々のお墓の管理料』ではありません
【お寺の場合は宗教的な制限がある】
お寺にお墓を持つと『宗教的な制限』があります。
お寺は仏教を信仰するための施設なので、お寺の敷地内にお墓を持っている人は、原則として仏教信者でなければいけません。
また、仏教信者であるだけでなく、そのお寺の宗派を信仰する必要があります。
そのため、「べつに宗派なんて何でもいいや」と宗派を軽視してお寺にお墓を建ててしまうと、後になって親戚間のトラブルに発展することもあるのです。
お寺の墓地を使うには、宗教的な制限は避けられないことを常に念頭に置いておきましょう。
【遠方へ引越した後に困る】
お墓を建てると、遠方へ引越した場合に困ります。
お墓は基本的に動かすものではないため、遠方に引越してしまうと、その後にお墓参りをするのが大変です。
もしかすると、引越し先にお墓を移したくなるかもしれません。
しかし、お墓を移動するには引越し先でもう一度墓地を探し、『永代使用料(墓地の使用料)』や『墓石設置の工事代金』などの大きな費用を支払わなければいけません。
遠方へ引っ越す可能性がある場合は、慎重に考えてからお墓を建てましょう。
【継承者不在の問題がある】
お墓は、代々にわたり継承されていくものです。
しかし、近年では、誰もお墓を継承することができず『継承者不在の問題』を抱える家が増えています。
お墓の継承者がいなければ、やがてそのお墓は【無縁墓】となってしまいます。
そして、一定期間を経過すると墓石が撤去されてしまうでしょう。
想いを込めて建てたお墓がずっと引き継がれるよう、その後の継承者についても考えておきましょう。
【廃寺や霊園閉鎖のリスク】
お墓は『寺院』や『霊園』に建てることが多いです。
そして、寺院や霊園は墓地全体を管理し、利用者が安心してお墓参りできるように努めます。
しかし、寺院や霊園は《管理者がいなくなる》《経営状況が悪化する》などの理由により廃寺または霊園閉鎖となることもあるのです。
そうなると、墓石の撤去や移動を余儀なくされる可能性があります。
寺院や霊園から墓地を借りてお墓を建てなければいけない以上、廃寺や霊園閉鎖のリスクは受け入れるしかないでしょう。
【寺院や霊園との繋がりができてしまう】
先述したように、お墓を建てると寺院や霊園とのさまざまな付き合いが始まり、いろんな案内が送られてきます。
案内の中には、お盆や法事などの定期的な供養の案内がありますので、大事な供養を忘れる心配が減ります。
しかし、供養に対して消極的な人にとっては、そのような案内が煩わしいと思うかもしれません。
霊園の場合は、供養に関する案内を停止してもらうこともできますが、寺院の場合は認められない可能性が高いです。
このように、人によっては寺院や霊園との繋がりがデメリットにもなることを心に留めておきましょう。
《まとめ》
お墓を建てると、ご遺骨を納める場所が確保できたり、故人との繋がりを感じられる、というメリットがあります。
しかし、お墓を建てて維持するためには費用がかかり、継承者の問題、遠方への引越し、寺院や霊園との付き合いがあるなど、考慮すべきデメリットもあります。
お墓を持つと、納骨場所が確保できる一方で、残された家族の以後の生活にも大きな影響が及びます。
お墓を建てるときは、メリットとデメリットをよく理解し、家族でしっかりと話し合って決めましょう。
《金剛院にはさまざまな形式のお墓があります》
金剛院では、一般的なお墓だけでなく、屋内(ロッカー)墓、樹木葬、個別永代供養墓、合葬墓などさまざまな形式のお墓があります。
きっとあなたのご希望に合ったお墓がありますので、ぜひ一度ご見学ください。
★他にもいろんな記事がありますので読んでみてください。